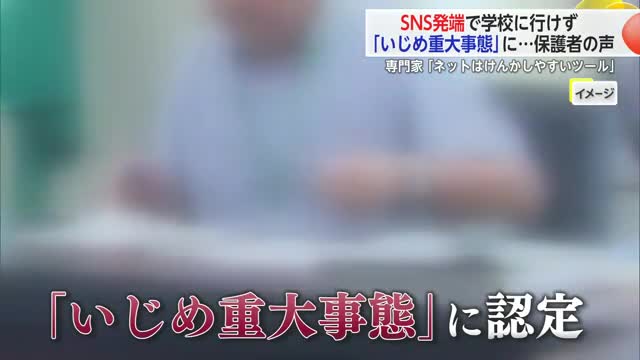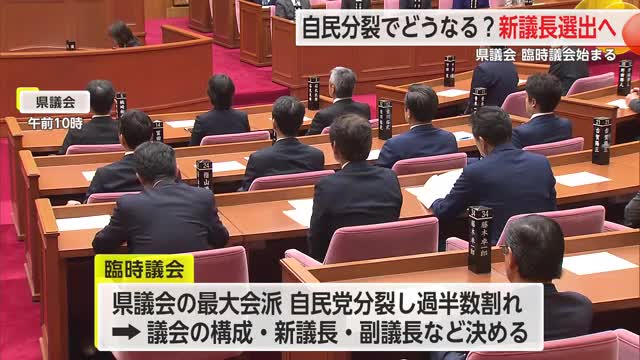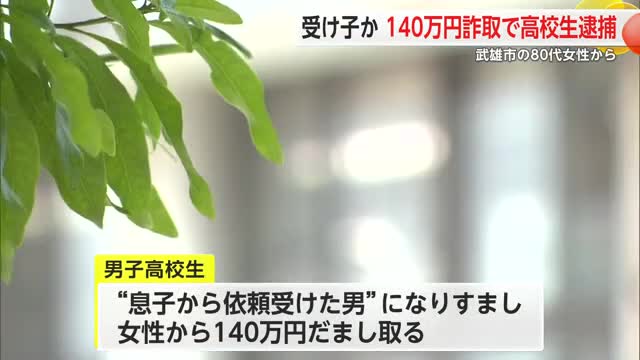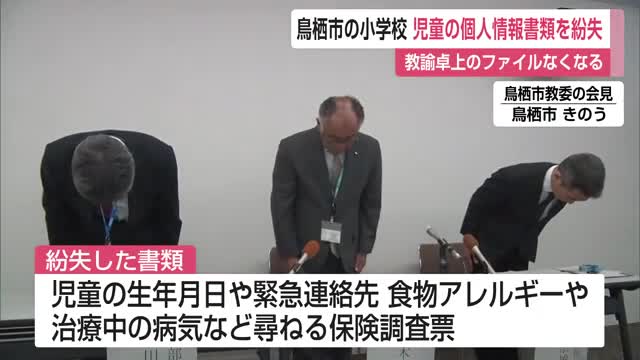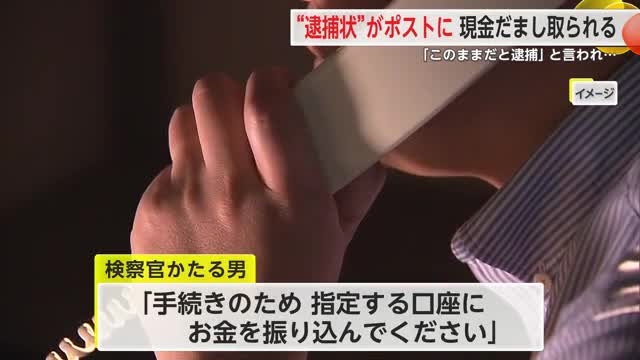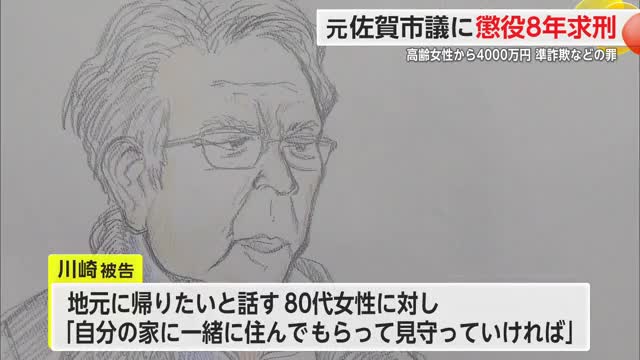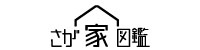佐賀のニュース
学校で「あだ名」禁止広がる 職場では上司に「さん付け」!?【佐賀県】
2022/06/27 (月) 19:15

みなさんは子どものころ、何というあだ名で呼ばれていましたか?学校現場でいま、この「あだ名」ではなく、さん付けで呼ぶ動きが広がっています。
見かけの性別との違和感を持つ人たちを尊重したり、ハラスメントやいじめを避けるなど、小さいころから人権意識をはぐくもうというものです。
解説主幹の宮原さんです。
宮原さん、県内の学校現場でもあだ名禁止なんですか?
【宮原拓也解説主幹】
学校現場では賛否両論あるようです。
例えば、私の場合ですと「ター坊」とか「タク坊」とか、お互い傷つけない、いわゆる愛称は、人間関係のクッションだったり、親しみを込めるものです。
一方、身体的な特徴などから、子どもは残酷な命名もうまいですからね。
人権や差別問題が専門の佐賀大学教育学部教授の吉岡剛彦さんにあだ名問題について聞きました。
【宮原拓也解説主幹】
学校現場で、あだ名ではなく「さん付け」で呼ぶ動きが、県内でも広がっている。
どう思うか。
【吉岡剛彦 教授】
私自身は基本的には賛成。
さん付けをすることによって、相手に対する敬意を表すことができるし、さん付けした後の言動、相手に対して丁寧で敬意を込めた行動につながると考えられる。
【宮原拓也解説主幹】
英語で言えばニックネーム。
ニックネームのレベルであれば問題はないが、あだ名は、身体的特徴を得てして言いがち。
これがいじめなどにつながる、ということでしょうね。
【吉岡剛彦 教授】
英語のニックネームの場合は、正式名称を縮めるというものが多い、あだ名の場合は身体的特徴をやゆするものになりがち。
呼びかける方は親しみを込めて言っていたとしても、受け取る方が嫌だという気持ちがあれば、ハラスメントでもそうだが、被害者が嫌だと思えばハラスメントに認定する、というのと同じ考えで、あだ名についても、本人が嫌だというのであれば、やはり避けるべき。
【宮原拓也解説主幹】
茨城県水戸市の私立小学校では、さん付けを校則で義務付けた。
この校則化についてはどう思う。
【吉岡剛彦 教授】
校則がどれくらいの拘束力を持つかは、学校ごとによると思うが、校則でまで呼び方を定めるべきかとなると、私も疑問に感じるところがある。
【宮原拓也解説主幹】
インタビューに出てきた水戸市の私立学校の場合、校則でさん付けを決めたのは10年前で、以後あだ名によるトラブルが少なくなったそうです。
人権問題とからめて言えば、男女別だったクラスの名簿についても、男女一緒にして五十音順に並べる「混合名簿」が、他県ではかなり以前から始まっています。
佐賀県では一昨年度、2020年度から、ようやく小中高すべての公立学校で、この混合名簿になりました。
男女別で、順番も男が先、というのが当たり前だったのですが、これから育つ子どもたちは、男女の垣根がより少なくなります。
【宮原拓也解説主幹】
学校での呼び名だけでなく、家族間の呼称、あるいは会社での上司、部下の呼称については、どう変化していく?
【吉岡剛彦 教授】
まず家族に関しては、問題になっているのは、夫をご主人、妻を家内、家のうちにいる人、と呼ぶのが慣習化している。
それに代わるものが今のところ存在しない。
パートナーとか、人によっては夫に「さん」を付けて「夫さん」、「妻さん」といった実践をしている人もいる。
最初は違和感があるかもしれないが、違和感を込みであえてそういう実践をすることで、主人、家内という言葉が持ってる問題を見直していこうという動きが広がっていけばいい。
【宮原拓也解説主幹】
会社の上司、部下。
これも「なになにさん」ということになるんでしょうか。
【吉岡剛彦 教授】
さん付けが持っている効用というのは、関係を対等化する、フラット化するという効果がある相手のことを「なんとか部長」「なんとか課長」というのは敬意も込められているが、目上の人ということになるので、どうしても言いたいことが言えない、言うべき意見が出てこないという雰囲気をつくるのと裏腹、裏表だと思う関係をフラット化することによって、モノが言いやすい雰囲気をつくることにつながるという意味では、そういう実践をする会社も増えてくるかもしれない。
【宮原拓也解説主幹】
私が今日から部下にさん付けしたら、異様に思われるかもしれません。
【吉岡剛彦 教授】
最初はやはり違和感があるし、よそよそしい感じもすると思うが、日常的な風景になっていくと、むしろ心地よい関係、新しい関係性が出てくるかもしれないですね。
【宮原拓也解説主幹】
国連で「女性差別撤廃条約」が採択されたのが、1981年。日本が批准したのが85年で、翌年、男女雇用機会均等法が施行されています。
しかし、「子どもの権利条約」が採択されて30年以上たっていますが、日本では子どもの権利を守るという視点での政策は遅れています。2022年になって、こども基本法が成立し、2023年4月から「こども家庭庁」がスタートします。
不登校の問題や児童虐待などが深刻化するなかで、ようやく子どもの権利を国として守っていこうとの取り組みです。この流れでいくと、身近な「あだ名」禁止という動きは、これから広がっていきそうです。
見かけの性別との違和感を持つ人たちを尊重したり、ハラスメントやいじめを避けるなど、小さいころから人権意識をはぐくもうというものです。
解説主幹の宮原さんです。
宮原さん、県内の学校現場でもあだ名禁止なんですか?
【宮原拓也解説主幹】
学校現場では賛否両論あるようです。
例えば、私の場合ですと「ター坊」とか「タク坊」とか、お互い傷つけない、いわゆる愛称は、人間関係のクッションだったり、親しみを込めるものです。
一方、身体的な特徴などから、子どもは残酷な命名もうまいですからね。
人権や差別問題が専門の佐賀大学教育学部教授の吉岡剛彦さんにあだ名問題について聞きました。
【宮原拓也解説主幹】
学校現場で、あだ名ではなく「さん付け」で呼ぶ動きが、県内でも広がっている。
どう思うか。
【吉岡剛彦 教授】
私自身は基本的には賛成。
さん付けをすることによって、相手に対する敬意を表すことができるし、さん付けした後の言動、相手に対して丁寧で敬意を込めた行動につながると考えられる。
【宮原拓也解説主幹】
英語で言えばニックネーム。
ニックネームのレベルであれば問題はないが、あだ名は、身体的特徴を得てして言いがち。
これがいじめなどにつながる、ということでしょうね。
【吉岡剛彦 教授】
英語のニックネームの場合は、正式名称を縮めるというものが多い、あだ名の場合は身体的特徴をやゆするものになりがち。
呼びかける方は親しみを込めて言っていたとしても、受け取る方が嫌だという気持ちがあれば、ハラスメントでもそうだが、被害者が嫌だと思えばハラスメントに認定する、というのと同じ考えで、あだ名についても、本人が嫌だというのであれば、やはり避けるべき。
【宮原拓也解説主幹】
茨城県水戸市の私立小学校では、さん付けを校則で義務付けた。
この校則化についてはどう思う。
【吉岡剛彦 教授】
校則がどれくらいの拘束力を持つかは、学校ごとによると思うが、校則でまで呼び方を定めるべきかとなると、私も疑問に感じるところがある。
【宮原拓也解説主幹】
インタビューに出てきた水戸市の私立学校の場合、校則でさん付けを決めたのは10年前で、以後あだ名によるトラブルが少なくなったそうです。
人権問題とからめて言えば、男女別だったクラスの名簿についても、男女一緒にして五十音順に並べる「混合名簿」が、他県ではかなり以前から始まっています。
佐賀県では一昨年度、2020年度から、ようやく小中高すべての公立学校で、この混合名簿になりました。
男女別で、順番も男が先、というのが当たり前だったのですが、これから育つ子どもたちは、男女の垣根がより少なくなります。
【宮原拓也解説主幹】
学校での呼び名だけでなく、家族間の呼称、あるいは会社での上司、部下の呼称については、どう変化していく?
【吉岡剛彦 教授】
まず家族に関しては、問題になっているのは、夫をご主人、妻を家内、家のうちにいる人、と呼ぶのが慣習化している。
それに代わるものが今のところ存在しない。
パートナーとか、人によっては夫に「さん」を付けて「夫さん」、「妻さん」といった実践をしている人もいる。
最初は違和感があるかもしれないが、違和感を込みであえてそういう実践をすることで、主人、家内という言葉が持ってる問題を見直していこうという動きが広がっていけばいい。
【宮原拓也解説主幹】
会社の上司、部下。
これも「なになにさん」ということになるんでしょうか。
【吉岡剛彦 教授】
さん付けが持っている効用というのは、関係を対等化する、フラット化するという効果がある相手のことを「なんとか部長」「なんとか課長」というのは敬意も込められているが、目上の人ということになるので、どうしても言いたいことが言えない、言うべき意見が出てこないという雰囲気をつくるのと裏腹、裏表だと思う関係をフラット化することによって、モノが言いやすい雰囲気をつくることにつながるという意味では、そういう実践をする会社も増えてくるかもしれない。
【宮原拓也解説主幹】
私が今日から部下にさん付けしたら、異様に思われるかもしれません。
【吉岡剛彦 教授】
最初はやはり違和感があるし、よそよそしい感じもすると思うが、日常的な風景になっていくと、むしろ心地よい関係、新しい関係性が出てくるかもしれないですね。
【宮原拓也解説主幹】
国連で「女性差別撤廃条約」が採択されたのが、1981年。日本が批准したのが85年で、翌年、男女雇用機会均等法が施行されています。
しかし、「子どもの権利条約」が採択されて30年以上たっていますが、日本では子どもの権利を守るという視点での政策は遅れています。2022年になって、こども基本法が成立し、2023年4月から「こども家庭庁」がスタートします。
不登校の問題や児童虐待などが深刻化するなかで、ようやく子どもの権利を国として守っていこうとの取り組みです。この流れでいくと、身近な「あだ名」禁止という動きは、これから広がっていきそうです。
|
|
|
- キーワードから探す
佐賀のニュース
特集ニュース
DAILY NEWSランキング
こちらもおすすめ
全国のニュース FNNプライムオンライン
-
就任後初来日のオランダ首相が万博を訪問
2025/04/23 (水) 01:44 -
イギリス空母「プリンス・オブ・ウェールズ」出港 夏ごろには日本にも寄港 自衛隊と合同演習へ
2025/04/23 (水) 00:53 -
「将軍」テーマの体験型カフェ開業 訪日外国人向けに日本文化発信
2025/04/23 (水) 00:33 -
京都府警「嘱託警察犬」新たに28頭を任命 事件捜査や祇園祭の警護にも
2025/04/23 (水) 00:15 -
「ルフィ」グループによる被害金のマネロンにも関与か 「アダルトサイトの未払い金がある」特殊詐欺で120万円をだまし取った疑いで男女3人逮捕
2025/04/23 (水) 00:15